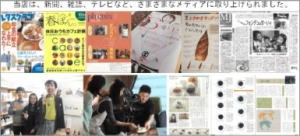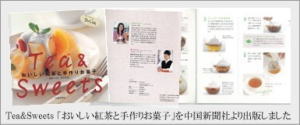答えを先言うと「沸騰した湯を使う」。これが簡単で、茶葉の美味しさを引き出す方法です。
紅茶をいれる時の湯の沸かし方や温度に関して
「紅茶の味は湯温で決まる」「紅茶には95℃の湯がベスト」「グラグラ煮立たせるから香りが飛ぶ、渋みが出る」のようなことが実しやかに囁かれています。
湯温が重要なのは間違いありません。湯温で紅茶の味は変わります。けれども、「沸いていない湯を使う」などがなければ、細かい温度まできにしなけれも大丈夫です。
なぜなら、茶葉の質が悪ければ、湯の温度をどれだけ意識しても、美味しい紅茶にはならないからです。
また、分量を間違えたり、ティーポットを使っていなかったり、蒸らし時間が適切でなかったりしたら「湯の沸かし方や温度」を気にしても意味がないからです。
とはいえ、「紅茶をいれる時の湯の沸かし方や温度に関して」気になっている人が多いようなので、少し掘り下げますね。
紅茶をいれる湯の温度
- 95℃の湯でいれた紅茶
- 100℃の湯でいれた紅茶
私の経験則ですが、このくらいの差なら、ほとんど人が味の違いに気が付きません。
私は専門学校で紅茶の授業をしているのですが、この実験をした時の学生達の声は「言われなければ分からない…何が違うの?」という反応です。気づくとしたら紅茶の温度の差。一方が少しぬるいのことには気がつく人がいます。何年もやっていますが、毎年こんな感じです。
紅茶の味の差があるとしても100点と98点くらいの差。
このくらいの差は日常によくあることです。同じように紅茶をいれたつもりでも、ちょっとしたことで微差はおきます。そして、こんな差は気にするようなことではありません。
95℃の湯を作るのは難しい
味以前に大きな問題があります。95℃や98℃や92℃の湯を作るのが難しいことです。
ピークに沸騰したら100℃とすれば、それは簡単なのですが、蓋を開け温度計で計って沸騰超直前の95℃とか98℃の湯を作って注ぐのは、現実的にかなり難しい…。“ムリっ!”て言いたい。
温度計で計らないで、沸騰超直前の湯で紅茶をいれることはできますが、沸騰直前を見極めて紅茶をいれるのは思いのほか難しいのです。沸騰しそうになったら見はってなければいけませんからね。
完全に沸騰した湯を作ることは誰にでも簡単にできます。
何か別のことをしていても沸騰には気が付くはずですし、少しくらい沸かし続けても問題はありません。
沸騰直前の湯、95℃の湯でいれた紅茶が、完全に沸騰させた100℃の湯でいれた紅茶より確実に美味しいのなら難しくてもそうすべきです。しかし、そんなことはないと考えるので、誰にでも簡単にできる沸騰させた湯で紅茶をいれることをおすすめします。

紅茶をいれる湯の沸かし方
- 汲み置きの水を沸かす
- 二度沸かしの湯
- 沸騰直前の湯
- 10分くらい沸かし続けた湯
- ピークに沸いた湯
この湯で紅茶をいれると、微妙には違いが出ます。
飲み比べをした人の感想は「言われなければ分からない」「なんとなく違う気がする」「これとこれはハッキリと違う」という感じです。違いに気付く人もいれば、気付かない人もいます。
大きな差ではありませんが、95℃の湯・98℃の湯・100℃の湯でいれた紅茶よりは差があります。
そして、汲み置きの水を沸かす、二度沸かしの湯、沸騰直前の湯、10分くらい沸かし続けた湯は、家庭で紅茶をいれるのでしたら、簡単に避けることができるはずです。避けることができるというよりもピークに沸いた湯を使えば良いのですから簡単ですよね。
美味しい紅茶をいれるためには、細かい湯の温度や沸かし加減を気にするよりも「汲み立ての水を沸かし、沸き立ての湯を使う」ことです。誰にでもできる簡単なことが美味しい紅茶をいれる近道です。
専門学校での紅茶の実験
専門学校で紅茶の授業をしていると言いました。100℃の湯と95℃の湯でいれた紅茶はほとんどの人が違いに気がつかないとも言いました。
別の実験。
同じ茶葉、同じ湯で紅茶をいれる
・ティーカップ1杯分(茶葉2g湯150cc)
・ティーカップ2杯分(茶葉4g湯300cc)
をティーポットで作ると紅茶の味が変わります。
この違いには半分くらいの学生が気がつきます。湯の温度ではほとんどの学生が味の違いに気がつきませんが、1杯分と2杯分では気がつく人が多い。中には両方で気がつかない学生もいますけどね。意外と紅茶の味の影響が大きいことが語られないんですよね。
90℃以下の湯を使うとなれば話が変わりますが、95℃くらいなら大差はありません。
紅茶をいれる時は沸騰したての湯を使いましょう。